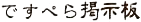湯川さんも政田さんも自分を語るひとでなかった。必要を感じなかったと云うよりはどうでもよかったのだと思う。これは編輯者によくあることで、自らが編輯する著者に代弁させる、すなわち黒子のさらなる裏面といった趣がある。政田さんは上戸で、彼の名古屋時代にわたしは何度か酒を酌み交わしている。しかし、塚本さんの前では決して盃を持つことはなかった。塚本がそれを嫌がったからである。従って、政田さんを下戸と思っているひとは多い。彼はそうした誤解を気にするような素振りすら表出さなかった。
大相撲の八百長問題でこのところ囂しい。日本相撲協会は八百長はなかったの一点張り。貴乃花や大乃国にとって八百長はあってはならない本質的問題だったが、現実には八百長が横行していた。またマスメディアの連中にとって八百長は相撲取りの大半が毒されてい、八百長は単に相撲協会の立前であったに違いない。なにを云いたいのかというと、本音と立前は常に入れ子構造にあって、なにが本音でなにが立前かは、ひとの立ち位置によって異なる。
テレビで某評論家が「立前は美しい、立前には美学がある」と分かったようなことを云っていた。日本相撲協会を弁護する発言だったが、本音と立前を識別できるひとだと、妙に感心させられた。感心させられた理由は彼は嘘をついていると云う点にある。前述したように本音と立前のあいだに境界線はない。常に揺れ動いている概念だからである。
余談だが、わたしは詩歌をよく読む。その評価は前述の嘘が含まれているかどうかの一点である。詩人でその峻別ができるのは谷川俊太郎の他、おそらく十名しかいない。一語、一語その言葉が正しいのか嘘なのかを吟味して用いる作家は寡ない。それは作品の巧拙を越えて大切なことである。翻訳の場合、その嘘があるかないかはさらに少数者になる。横文字を縦文字に変換するに止まらない。なにげなく用いる言葉にこそ、嘘は介在する。その嘘を刮げ落とし、かつ名調子に仕立て上げる高遠弘美など神業に近いものだと思っている。
さて、湯川と政田である。彼等は相手に応じてなにものにでも成り遂せた編輯者である。出遇った相手の数だけの顔を湯川さんも政田さんも持ち合わせていた。そこのところを誤解するととんでもない湯川像が政田像が誕生する。もっとも、彼等はにんまり嗤ってそれを許しただろうが。
レイアウトが崩れる方・右メニューが表示されない方:
>>シンプル・レイアウトへ
« 湯川さんについて追記 | メイン | 年内閉店 »
裏面 | 一考
|
←次の記事 「年内閉店」 |
前の記事→ 「湯川さんについて追記」 |

このページについて...
アーカイブ
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- タイトルリスト
カテゴリー
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34