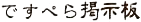何時も書いていることだが、読書とは生きることであり、個々の人生そのものである。作家は書くことを生きるのであって、読書人は読むことを生きる。学研文庫版「後方見聞録」の解説で書いたのはそのことに尽きる。当然、自らの生に相応しい書物があれば相応しくない書物もある。要するに、好きな書物は個々に異なる。その差違を重んじるがゆえに、大量に売れる書物を訝しく思う。
おニャン子クラブとAKB48、出自は違うがモーニング娘といった個々の差違でなく、シンクロが売りのグループがある。この場合、個は問題にならないのでメンバーは次々と替わってゆく。端から核になるものがないので、悉くが代用品である。ここでベーコンを持ち出せば揶揄となる、現代ではアイドルすらが代用品で有効なのであろう。
昔はクレイジーキャッツ今はAKBと云いたいところだが、前者に顕著なナンセンスは後者には見られない。AKBは素人ゆえの直向さはあるもののおよそ能転気なグループである。その調子のよさが時代に受けたと解するべきか。個の否定に甘んじるか、それともグループはわたしで持っているとの錯覚に身を任せるか、いずれにせよ当人達に覚悟はなにひとつとしてあるまい。
この消息はアイドルに止まらない。昔、サーニンが発売禁止処分になった。自殺者が続いたからである。往時の書物の社会的地歩と現在のそれではあまりにも異なる。エンターテインメントと云えば聴こえは良いが、まるで読書から人生が消え失せたようである。きっと消え失せたのは人生だけではない。
個人の価値や好みを集計して弾きだした公約数を並べたものがベストセラーだとわたしは思っている。そうとでも思わなければベストセラーなるものを理解できない。多数の支持を得るにはなによりもまず平均的でなければならない。当然ながら、読者も平均的人間ということになる。このふたつが仕合せな結婚に成功したのが現代であろう。
書き手と読み手に限らず、なにもかもが置換可能な世界、個のない世界、貌のない世界の浸食がはじまった。私流に云えば、情念のない世界ということになる。
レイアウトが崩れる方・右メニューが表示されない方:
>>シンプル・レイアウトへ
ベストセラー | 一考
|
←次の記事 「宿題」 |
前の記事→ 「若葉マーク」 |

アーカイブ
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- タイトルリスト
カテゴリー
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34