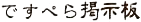ポスターと云えばコーベブックスでの最初の仕事「タロット展」を思い浮かべる。当時、西武百貨店にいらした草刈順さんにポスターの制作を依頼した。最初のポスターは神戸展専用のもので、阪急、阪神の駅などに貼り出した。ところが、貼っても貼っても持って行かれる、一日として貼ったところにないのである。後日聞くに、ポスターを切り抜いてタロットカードを造ったそうな。1974年6月のことだが、当時はかくまでタロットが珍しいものだった。
同年末、池袋の東武百貨店で東京展を開き、一挙にタロットは知られるところとなったが、主宰コーベブックスと小さく刷られたポスターが東京中の地下鉄に貼り出された光景には誇らしさを感じた。
徒し事はさて置き、笹目浩之さんの著書「ポスターを貼って生きてきた」がパルコ出版から発行された。ポスターハリス・カンパニー主持であり、近著に「ジャパン・アヴァンギャルドーアングラ演劇傑作ポスター100」がある。新宿ゴールデン街からはじまって、渋谷、下北沢、六本木、西麻布、青山等々の飲み屋に演劇のポスターを貼るのを生業としている。
ナジャのクロちゃんは昔、ゴールデン街で文庫屋というバーを営んでいた。劇団状況劇場御用達の店で、笹目さんもわたしも常連客の末席を穢していた。彼のポスター貼りの歴史は文庫屋にはじまると云っても過言ではあるまい。それぐらい大きな契機を彼は文庫屋から得ている。「ネオン輝く夜の繁華街は、いわばぼくやスタッフにとって「舞台」だった」その舞台を「街のいたるところや人々の生活の中にまで演劇や芸術的なものを広げる」「実利実益しかない街に、演劇という虚構の世界、想像の世界への窓口となり入口にもなるポスターを貼りめぐらす」と云った彼の思いで染め抜いていった。
彼の脚本とは、「一日に貼る枚数は七十枚ほど、ポスターというのはまとまると案外重いもので、これだけで二十キロ程度の荷物になる。このほかに・・・ポスター貼りの七つ道具がある」、その「重いポスターを担いで一晩に何十キロもの道のりを歩きまわ」ること。一種の隙間産業といえようか。彼のユニークな人柄あっての商売と思われる。
今回の著書を頂戴した折、彼は文学とは関係のない本で恐縮ですが、と繰り返した。思うに、生業をポスターハリス・カンパニーと名づけた瞬間から彼の唯一無二の人生がはじまった。「貼ったり人生」結構、彼の存在それ自体を文学と云わずになんとする。
レイアウトが崩れる方・右メニューが表示されない方:
>>シンプル・レイアウトへ
「ポスターを貼って生きてきた」 | 一考
|
←次の記事 「企画書」 |
前の記事→ 「血圧」 |

アーカイブ
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- タイトルリスト
カテゴリー
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34