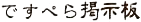子供のころ、自分の死を持ち歩くように、いつも詩集を小脇に挿んでいた。有明、清白、朔太郎、そして吉岡実であり田村隆一だった。そこへ相澤啓三の詩集が加わった。
先日「冬至の薔薇」が書肆山田から上梓された。彼の詩集はいつも遺書の形を取る、それは分かっているのだが、今回は特にその感が強い。巻頭を飾る「冬至の薔薇」と巻末に置かれた「まだ見ぬかたの花」のコレスポンドンス、「アントン/アントン」の後方に位置する「革命」と「非在のノイズ」、そして「島」、詩の一篇、一篇がどうしようもない地歩を占める。彼の詩は順序を違えると理解できなくなる。かくまで冷徹な計算によって組み立てられた詩集が他にあったろうか。
詩は私でなければならぬ。この当たり前のことをひとは等閑(なおざり)にする。私小説という言葉が遣われた意味はともかく、「冬至の薔薇」一冊はすぐれて私集といえようか。
作品が作者を離れて独立するというようなことをしたり顔で宣うひとがいるが、作品はその人そのものである。人品骨柄のことごとくは作品に如実に反映される。人格が不明瞭な作品は精神と情念との相剋が未分化なだけである。そんな詩が持て囃される時代にあって、相澤啓三の私はまさに詩として屹立する。
心ある人は戦中戦後を生きてきた、革命のためだけに。「沈黙の音楽」から「マンゴー幻想」に至る作品にはその苦衷が詳述されている。その「心」を相澤さんはかなぐり捨てたようである。形振りを構わなくなった詩人の絶叫がここには流れている。静と動、あるとないと云った弁証法を越えて、相澤啓三は非在のノイズのなかに深く身を沈める。
あらゆる言葉がけがされるなかで
「革命」ほど汚辱にまみれたものはない
上記の二行から「革命」は書き始められる。長い詩なので引用はしたくない。詩の引用がなにを意味するかは掲示板でさんざん書いてきた。ただ、最初と最後だけを引用する。後は読み手次第である。
言葉よ眠れ 唾されるがままに
いま言えないことを浮かび上がらせるために
深い傷の底へ 言葉よ沈め 見えないアクションをもって
踏んでゆくしかないそこが ペダルとなって鳴る
不可解な革命 もしくは永遠に回帰して心を乱しつつ
光の繭をつむいでは闇に呑まれる音楽
革命のあらゆる方策があらゆる刃が自分に向けられてゆく。「どこでもいい 自分でないところなら」。子供のころ、ひとはなにものかを睥睨して生きている。そしてある日気付く、睥睨すべき対象はどこにもなかった、ひとり、自分自身を除いて。(文中敬称略)