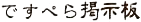意識が、自分という存在のひとつの側面にしか過ぎないことはよく分かる。意識が消失したところで、やがて意識は戻ってくる。その間にも存在はあるのであろう。ただ、意識が失われて行くときに次に現れるであろう意識を想定するのは不可能である。それっきりになることだって起こりうる。
それにしても、意識が失われていくときの苦痛、全身の緊迫感はなんだろうか。背中のかゆみが一瞬にして全身に拡がる。非常事態のサイレンが身体中に谺する。知覚は視力から奪われ、皮膚感覚がなくなり、全身が熱のかたまりとなって、純白の残像を結ぶ。やがて真っ白の像が汗を迸らせる。なにかから逃げだそうとするのだが、その対象がなんだか分からない。知覚を取り戻そうと必至になればなるほど、身体は制御不能になってゆく。身体の先端から痙攣がはじまる。痙攣が腰へ来る頃、無駄な足掻きを諦める。ただただ、汗で濡れそぼった頭と顔と熱そのものが不愉快である。誰か熱を拭き取ってくれないだろうか、そうすれば安らかに眠れるのにと。記憶が跡切れ、時が失われる。
記憶が再開されるとき、それはいつもなにかしら冷たいものからはじまる。冷たい地面、冷たい壁、涼しい風、氷か鏡のように凍てついた手、そうしたものに触れたもしくは触れられた気がして徐々に目覚める。目覚めと同時に記憶を辿るのだが、肝心なところは虚ろである。この時になにかを掛け違えると再び昏睡状態に陥る。そのなにかは名状しがたい。身体は常に消失の方向へ向かっている。従って気を張りつめなければならない。おそるおそる半眼で遠くを見る。見慣れた光景がおぼろに浮かび上がってくる。あと一息、蔚藍天を取り戻すにはあと三十分ほどの我慢である。
意識消失を誰かさんに擬えてわたしは「小さな死」と名付けている。意識消失が繰り返されることによって、思いも知覚も身体も垣根がなく、存在はひとつの「もの」であることがよく分かる。だからこそ死を直前まで描写できても死そのものは理解できない。死は突然、天から舞い降りてくる。抗いようがない。例え、契機が自死であったにせよ、やはり死はにわかに翔け降りてくる。生活苦とか心象風景によって死を撰ぶほどわたしは軟弱でない。しかし、自らの意志によってどうこうなるようなものではない。死は想像を絶するほど暴力的である。