 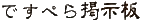 1.0 1.0
|
 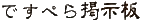 1.0 1.0
|
« 前の記事「弁証法の魔」 | | 次の記事「軍産複合体」 »
グザヴィエル・ゴーチエの「シュルレアリスムと性」が平凡社ライブラリーから再刊された。訳者は三好郁朗さん、かつてルネ・クルヴェルの「ぼくの肉体とぼく」を私は編輯している。「シュルレアリスムと性」が最初に上梓されたのは1974年、朝日出版社からであった。当時、評判だったケイト・ミレットの「性の政治学」と一脈相通じるきわめてアクチュアルなインパクトを内包したエッセイである。
ミレットはD・H・ロレンス、ヘンリー・ミラー、ノーマン・メイラーのような性の文学の作家たちを男根中心主義と批判し、彼らの状況判断が誤っていて、作品の偏向が有害であると指摘する。他方、フロイトの男根中心的な理論体系、すなわち主観的秘教主義、禁欲、保守性などはそっくりそのままブルトンに受け継がれてい、それこそが革命に対するシュルレアリスムの裏切りだとゴーチエは糾弾する。
性差別を温存したままでの性の解放など、所詮は男性がよりよく女性を享有するための強弁であり、反動的改良策でしかない。自ら革命思想を自認したコミュニズムとシュルレアリスムが、結果として、性欲をその原理において抑制するに至った反革命性をゴーチエは明確に跡づける。 まことに手厳しいブルトン批判なのだが、当時の私の目には説得力があるように思われた。「シュルレアリスムと性」一巻は、私にシュルレアリスムとの決別を迫るものであったと言っても過言ではない。そして、女性の疏外状況の理想化、永続化を計る企てに抗議しつづけた倒錯的性愛実践者のルネ・クルヴェルに傾倒していったのも、ゴーチエの導きであった。
ラカンの影響が強いが、そのラカンやドゥルーズを経た今日ではいささかの問題点もある。同性愛の章で当然触れなければならないマイノリティの概念を考察せず、サド・マゾヒスムの章では否定するフロイトの理論からの解放をなんら試みていない等々である。しかし、その辺りをさっ引いても面白い、現在にあってなお有効なシュルレアリスム批判の書である。
種村季弘さんがつとに指摘するように、フロイト、ライヒ、マルクーゼという精神分析学の一系譜はシュルレアリスムの理論形成と深く重なり合っている。重なり合うのは構わないが、その反動的傾向は困ったもので、ネット社会の今日、その性差別の傾向はますますひどくなっているように思われる。「異常」であれ「倒錯」であれ、もしくは「男らしさ」であれ「女らしさ」であれ、性欲を常に性器的なものに閉じ込めようとする男性中心の文化が瓦解するのは何時なのか。男であれ、女であれ、なんであれ、そのような概念はどうでもよい。個々のひとはまず欲望の主体であると同時に欲望の対象である。それは対立する概念ではなく、融解し滲透しあうものでなければならない。エロティシズム、ひいては性の問題こそが、革命の起源の場であり実践の場であらねばならない。
平凡社ライブラリー版には旧版の「訳者後記」も収められている。六十年代の思想的激動の一端が垣間見られる傑出したエッセイである。また「訳者後記」に出てくる「君」は若くして縊死した大槻鉄男さんのことである。セリーヌやブルトンやシュペルヴィエルの名訳を遺したフランス文学者にして詩人。七十年代、私の京都時代は彼と共にあった。
« 前の記事「弁証法の魔」 | | 次の記事「軍産複合体」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

