 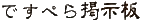 1.0 1.0
|
 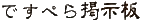 1.0 1.0
|
« 前の記事「神戸の泥鰌屋」 | | 次の記事「オホーツクの匂い」 »
高遠さんへ
じつはちりめん山椒について書かねばならないのですが、ネタがなくて困っているところです。こちらではしらす干し、「白簀乾」とも書くらしいのですが、上方ではちりめんじゃこ。もともとは徳島、香川が特産地で、阿波藩の淡路のものはよく識られています。
で、ちりめん山椒がどうしてどじょうの食べかたに化けたのかと申しますと、共に下世話な食い物という点で似てい、また食する側のなにかしら差別意識のようなものが感じられたからなのです。
ちりめん山椒がいつごろできたものか分かりませんが、最初は山椒の葉、青い実の醤油漬け(いわゆる有馬山椒)を用いるようになったのは後年のことらしいのです。
福岡のイワシのちり鍋、長崎のイワシ餅等々、いろんな郷土料理があるのですが、どうやら香川のいりこ飯がちりめん山椒の原形らしいのです。もっとも、いりこ飯はイワシのしょうゆ漬けを飯に加えたもので、趣がまったく異なります。いっそ大磯のたたみいわしや煮干し、ごまめ、たづくりの方が稚魚を用いるのでちりめんには近いのです。
ちりめん山椒といえば京都が有名ですが、歴史は九州、中国、四国の方が古く、例えば、播麿でクギ煮を造っているところは昔からちりめん山椒も造っています。「らしい」ばかりで申し訳ございません。どのようなことでも結構ですのでご教示ください。
ウナギなら日野草城や斉藤茂吉の「白桃」、火野葦平の「赤道祭」、獅子文六の「てんやわんや」などいくらでもあるのですが、ちりめん山椒はお手上げ。料理は食べるもので、書くものではなさそうです。
« 前の記事「神戸の泥鰌屋」 | | 次の記事「オホーツクの匂い」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

