 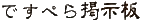 1.0 1.0
|
 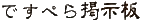 1.0 1.0
|
« 前の記事「黄金色の階調」 | | 次の記事「バザール」 »
「黄金色の階調」はかつて料理王国に著したものの改稿である。末尾に固定観念に対する否定的見解を書いたが、思うに、私の死生観やものの考え方は料理の調法や酒の味わい方から多くを学んでいる。例えば、穴子は焼くか蒸すのが一般的だが、刺身だと食べられないのだろうか、試行錯誤の末、洗いが穴子に似合いの調法だと知る。はなしはそこで止まらない、子をまぶすとどうなるのだろうか、あしらいはどうか、醤油は洗いには相応しくないからどうしようかと言った風に、連想ゲームは続く。また、懐石では同じ料理の繰り返しは避けなければならない。材料と調法を求めて、地方を行脚し書物を博捜しなければならない。料理とは間違いなく、一種の漂泊だと思う。
出生地の都合もあって、回りはやっちゃん、ぽん引き、女衒、娼婦、てきや、おかまといった裏社会のひとたちばかりだった。子供の頃はそれが嫌で、自己形成期への瞋恚を育んだのは福原という色街だったと、いまにして思う。抛り込まれた環境に従順(すなお)に馴染めなかった私はその対局に文学やそれを研究する文学者を置いた。理由はなにもない、なんとなくそう感じたまでのはなしである。
十代の半ばになってドストエフスキーやカフカやサルトルを読み、やはり物書きや文学者は人生の達人であって、すぐれた人品骨柄の持ち主なのだと、勝手に思い込むようになった。そう信じたが故に、書物の世界へ彷徨い込み、同時にさまざまな詩人、絵描き、小説家などと交流を深めた。
そして十代後半、いうところの全国区の詩人、文学者、書物研究家、書誌学者などと出遇う。しかるに、「バンビーについて-2」で書いた「鄙劣きわまりないものの考え方を文学だと嘯くような燕石」と最初に出遇ってしまったのである。彼は強度なヒステリー患者だと、後日、生島遼一さんや曽根元吉さんから指摘されたが、ときすでに遅く、手の施しようのない身体症状や解離症状との道行を強いられてしまったのである。ヒポクラテスの時代のヒステリーが子宮の病なら、あれは前立腺の病でなかったかと思う。子分を集めて常時集団ヒステリーの渦中にないと精神的葛藤が処理できない、福原のやっちゃんと同じ「困ったちゃん」そのものであった。
名前は伏せるが、某英文学者にして著名な書物研究家から「君は美しい書物を造るが中身がどうもねえ」と指弾された。「先生のおっしゃる中身があるものとは古典ですか、だとすれば、それは時代によって変わりますよね」「変わるわけないだろう、第一にどれが古典かを決める権威を有するのは私ぐらいなものだ、私は権威そのものなのだよ」。
丸山豊が主宰した「母音」時代からの友人で左翼文学の代表選手だった某詩人兼評論家と高木護さんのはなしになった。隣には夙に知られた女流作家もいらした。その隣人曰く「あのひととは血筋が違います」。ちなみに、私は高木護のファンである。
実名を隠しての書き込みはあまり意味をなさない。咨嗟するところは、物書きや文学者の多くは裏社会のひとたちにはないものを後生大事に携えていた、それは権威と権力であった。権威と権力の裏付けが知識であろうが格闘技であろうが渡世の筋であろうが同じ穴の狢である。神戸の広域暴力団の中枢にいたひと(ほんの一部だが)の方が配慮に闌け、複雑に錯綜したものの考え方を持っていたように思う。
それやこれやで、近頃、私は物書きや文学者、それと読書家、要するに知識人といわれる人種をほとんど信用しない。知識がそのひとのなかで解体され、追体験され、ものの考え方にまで伝搬されている例があまりにも少ないからである。解体されずにいるのは、前述の精神的葛藤が未処理のまま無意識領域に抑圧されていることになる。
国家、民族、宗教、言語、知識などが帰属や境界の基いになり、差別や排除のエネルギー源になる。また、
差別意識の生起の要因のひとつに国語教育がある。それは近代国家の成立の過程あるいは以降に登場したものなのだが、ナショナリズムの発生と国家語意識の発揚との関係については別の機会に譲りたい。ここで述べておきたいのは、イギリスで誕生した近代国家との概念は「万人の万人に対する闘争状態」からの脱出を願っての思想原理のひとつであり、国語はそれら思想をひとに伝えるための道具の共有化であり、知識はその道具の有効性を高めるための薬味だったということである。ホッブズからロックを経てルソーに至るまで、消息は同じである。
複数の国語という時限爆弾を抱えるスイスやベルギーと日本のように公用語と日常の生活言語が重なっているような国では条件が異なる。そして層なるが故であろうか、「八紘一宇」であれ、その逆の「総括」であれ、どうして日本人は右も左も国家主義的発想から遁れられないのか不思議に思う。それともヒステリカルな中でしか日本人は生きられないとでも言うのであろうか。
このところ、差別と排除について執拗に書くのは、排斥の論理がヒステリー症状ときわめて似ているからである。演技性、自己中心性、情緒不安定性、誇張された言語への依存性等々、陶酔した没我状態と強い虚栄心が綯い交ぜになるところにヒステリー性格の特徴がある。ヒステリー身体症状の典型が疼痛だが、疼痛は風の病ともいう。悪い気がナショナリズムでないことを願うばかりである。
言葉や知識を自己顕示性の表明から解放するのは、取りも直さず言葉それ自体の開放になる。言葉を国語教育から、さらには帰属や境界という頸木から解き放たなければならない。いつの世にあっても文化は常にネガティブなものの意義を担保する。だからこそ、言葉は常に破戒されなければならない。破戒するとは、作家の主体的創造力の場に引き戻すことに他ならない。そして言葉の暴力的な破戒のなかにしか「主体的創造力」はない。
« 前の記事「黄金色の階調」 | | 次の記事「バザール」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

