 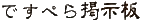 1.0 1.0
|
 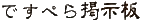 1.0 1.0
|
« 前の記事「キルケニー」 | | 次の記事「キルケニー」 »
内山さんへ
アバウトで結構です、お待ち申しております。なにとぞよろしくお願い致します。
拙い書き込みをお読みいただき恐縮です。「最短でも三十回は会ってはなしをする必要がある」はひととのコミュニケーションの煩雑さを、「あなたの場合はあいだに作品が介在しましたから」との文言は彼の作品が文学になっているとのわたしの意思表示を繰り返したまで。
先だっての書き込みでどこかの出版社がひろくレビューを求めていらっしゃいましたが、概要がレビューとは笑止。とは申せ、概説に好き嫌いもしくは良い悪いを付け足せば書評と勘違いなさっておられる方が多いように思われます。書評に限りませんが、ものを著すに当たって留意すべきは概要と鉤括弧を用いてはならないとの二点だと思うのです。
概要で用が足りるならなんのための書きものなのか、五十枚なら五十枚、百枚なら百枚が必要だから書くのであって、それを概説にしてしまえば伝わるものはことばの意味内容や表象に限られてしまいます。それら表象から遠く逸脱してゆく書き手の影や分身にこそ肉声が罩められているかもしれないのに。
鉤括弧すなわち引用にはさらにふたつの問題点が加わります。こんなものを読んでいるぞとの自慢がひとつ、今ひとつはそれほどに巧く表現できないから引用するとの逃げの一手。前者は可愛げがあってまだ許せるのですが、後者は困ります。だって、うまく書けないのなら書くのを止めればよろしいのであって、なにをじたばた騒いでいるのかと言いたくなります。なんでも書きゃあいいというものではないのです。
まずは鉤括弧を外せばよいのです。外すことによって盗作と言われるのがいやなのであれば、それを読み解いて自分の言葉に置き換えれば済みます。読み解くとは自らの言葉への置換を指すのであって、置換の結果がいかに稚拙であってもそれが自分の実力と知るべきなのです。
引用との行為はものの考え方までをひとに委ねることになりかねません。それは危険な思想に繋がります。文学はどこまでも個の営みです、されば読み手にも個が強いられます。文学に随伴するのは「なにかしらもっと大きなディメンション」につねに向き合おうとする意志、言い換えれば能動的マイノリティ哲学に違いないと思うのです。
« 前の記事「キルケニー」 | | 次の記事「キルケニー」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

