 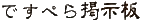 1.0 1.0
|
 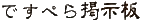 1.0 1.0
|
« 前の記事「渋谷・地下の一角に四谷シモン氏の作品が展示中」 | | 次の記事「私刊本二点」 »
不眠やフラッシュバックがどうして起こるのかを解明するには、患者に症状を尋ねるだけでは駄目で、状態を見極めながら根気強くはなしを聴き、相手の内側に入り込まなければなにも見えてこない。それとおなじで、詩歌を繙き、そこに認め綴られたことばの意味を訊ね、内容を追ったところで作品のひとつの側面をなぞることにしかなりません。要するに、選択された文言やその作家の語彙を気にしていては詩は読まれないのです。意味内容や表象を読み解くのと同時に、そこから遠く逸脱してゆく書き手の影や分身、いわば著者の搏動のようなものを諒解しなければ、書物を繙いたことにはならないのです。
著者によって選ばれた文言にのみ注意が向けられていると大事なものを見失う、と前述しました。同様に、なにかしらもっと大きなディメンションがあって、テーマはそのなかで取り扱われる些細なパーツのひとつに過ぎないのかもしれません。月並な批評家のスタンスに気を取られていると、詩の本質は指のあいだからみごとにこぼれ落ちて行きます。なにかテーマがあって、もしくは特定の作家の作品からテーマを取り出し、それだけについて書く、というのが長年にわたって返覆されてきた旧態依然たる批評家的こわばりでなければなんなのでしょうか。詩はアナロジーで書かれます、種村季弘さんがよくおっしゃる「アナロジーのアヤだけ」は表現行為の核心をついたことばです。分かりやすくいえば、すぐれた詩は一篇の探偵小説のようなものだと思えばよいのです。
オリジナリティーを声高に宣うひとは、自分の情念を表現すれば芸術になると信じ込んでいます。芸術は過去に鑑賞したものやそれらから得た識見や情動のなかから、いま必要なものを抽出し寄せ木細工のように組み立てていく、ただし既に用いられた組み合わせではなく、新しい組み合わせが必須の条件となります。その調烹にこそ詩人の真骨頂が、さらなるディメンションがあるのであって、個性ならまだしも、独創などというものは芸術の世界には存在しないのです。
一方で、選択に立場の闡明があるとよく云われますが、選択とはあくまで立場のこちら側に蹲居するものであって、いわば作品の装いに属するものではないかと思うのです。たしかにそれも作品の大切な一部なのですが、重層するさまざまな側面を繙いてこその読書であり、それを怠れば書蠹との謗りを免れないのです。「作品の向こう側から押し寄せてくるメタファーとの鬩ぎ合いのなかにこそ、読書の醍醐味がある」と私が執念く言い続けるのは理由があってのことなのです。
さて、以上のことをこころにとどめて読まねばならない、とんでもない詩集が出版されました。相澤啓三さんの詩集「マンゴー幻想」がそれで、四月三十日に書肆山田から上梓されたのです。「とんでもない」と書いたのは他でもない、吉本隆明から谷川雁に至るまで戦後詩人の多くが挑戦して果たせなかった、文学と政治とテロルとの三位一体に相澤さんが明確なかたちを与えたからなのです。ギリシャの先哲を持ち出すまでもなく、元来、文学と哲学的思索と政治はよく似た志向性を持っていました。それは破砕された現実と現実を、そして現実とひとの存在についての意識をつなぎ合わせる役目を背負っていたのです。背負っていたはずなのですが、いつかしらず散り散りになり、文学が内省という二元論の片割れに特化するところから、有効性すなわち現在形を失っていったのです。
一方、美はそのままで全体だから分析はできません。逆にいえば、分析可能な知性で拵えたり、知性で分析できるものは美ではないのです。その美と知性という異質な領域にアナロジーでもって橋梁を架けようとの困難な企てが立てられました。例えばボードレールのコレスポンダンスやランボーの錬金術のような詩がそれで、それ自体が一種のエステティークな感覚を内包しているのですが、決して美にとどまるものではなく、より大きなディメンションを舞台にした運動としての文学と解釈していただきたいのです。
表題作「マンゴー幻想」にあって、現実はモザイク、一種の象眼のようなものとして再構成されていきます、自らの恥辱の証しとして。諍いを生み出す不信と対立、それら不信や対立の不毛の証明として、不慥かな成り立ち、かりそめの来歴、姑息な思惟等々が累ねられてゆきます。そして隙間を塞ぐように立ち顕われる恥辱の証しとしての自責。償われることのない、贖われることのない、謂わば幻日のふたつの光点のあいだを立ち徘徊る暫定的な存在、繰り返される迷いのなかにしか不毛を解く鍵はなく、繰り返されるためらいのなかにしか現在形はないのです。
時代に脊を向けたところで拵えられる閉戸された作品はいくらでもあります。しかし、時代と正面から向かい合い、かつ時代に対して有効性を持つ詩というのはほとんど例がないのです。おそらく、相澤さんは日本語による詩の歴史についぞ存在しなかった、まったく新しいタイプの詩を創出しました。ジャン・ジュネの「恋する虜」やピエール・ギヨタの「500万人の兵士の墓」の精神の系譜に列なる作品がはじめてわが邦に誕生したのです。
中井英夫の死後、十年の沈黙を経て、詩集「五月の笹が峰」「孔雀荘の出来事」、歌集「風の仕事」が堰を切ったように上梓されました。交錯する憐憫と流涕、愛憎半ばする戦友との別れにくだされたとどめの一撃のような詩群でした。そのあとに、それらを真向から否定するような新しいホモロジーを内包した詩集「マンゴー幻想」が顕れたのです。読み手を突き放し、読み手を拒否しかねない気配や振動を「マンゴー幻想」は内包しています。前書きを添えざるを得なかった理由はそこのところにあります。大方の読者はくっきりと一つ相澤作品のイメージをもたれ、そのイメージを拡げよう、もしくは自らの期待に添うように読み取り、解釈しようとされるに違いないのです。ところが、今回の詩集はリップ・カレントのようなもので、巻き込まれると思いもかけない遠いところまでもっていかれます。
本書で取り扱われた対象は著者にとってかならずしも取り扱うべき対象ではなかったと書けば、アイロニーに過ぎましょうか。対象をだしにして、対象に託つけて精神の循環を、三次元を超えた新たなユークリッドのストイケイアのようなものを相澤さんは示唆されたのです。失礼ながら、相澤さんは私などよりもお歳を召された方なのです。しかるに、今回の詩作品で晰かにされた恥辱と自責、出現と消滅の弁証法、瑞々しい柔軟さとかいろぐ屈折、休むことなく滲透しあい、そして震蕩しつづける精神の放縦、伸縮自在な詩精神、それらはまさに驚愕であり、慴れでした。個としての相澤啓三そのもののエピファニーを深く感じさせられたのです。
ガンジス川中流域のバイシャーリー市郊外にあるマンゴー樹の園林で釈迦は維摩経を説いたといわれます。文殊は垢と浄らかさは究極的に不二、無言無説であるとことばで表現したのに、維摩は沈黙でもってそれを示したとされます。過去の実績を棄て、名声や立ち位置を顧みず、新たな詩の世界へ躍り出たひとりの詩人、相澤啓三さんにとって過激と柔軟さは云うまでもなく不二、作品の裏にしつらえられた沈黙、その沈黙からとめどなく湧き出るメタファーの洪水をいかに受け止めようか。
追記
ですぺら通信にかたちを変えて書き込んだものをひとつにまとめました。先日高橋睦郎さんとの晤語にめぐまれ、また後日「るしおる」に掲げられた高橋さんの「テロルの木をめぐって」を読んで、まとめる必要に駆られたのです。「ものを書く最良の苗床は孤独」とは高橋さんの口癖ですが、相澤さんの十年におよぶ沈黙(孤絶)に対する畏敬の念を私なりに著したいと思ったのです。ちなみに、詩集「マンゴー幻想」に瞠目なさったのは現時点では佐々木幹郎さんと高橋睦郎さんのみ。詩集の表題にもなっている「マンゴー幻想」を引用したかったのですが、作品は必要最低限のことばで成立しています。従って、一部分を抽出するような無礼は私にはできません。「マンゴー幻想」の定価は2800円、購入をお薦めする次第。
« 前の記事「渋谷・地下の一角に四谷シモン氏の作品が展示中」 | | 次の記事「私刊本二点」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

