 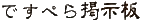 1.0 1.0
|
 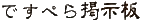 1.0 1.0
|
« 前の記事「しばしば書き込みをして申し訳ありません」 | | 次の記事「新潟麦酒」 »
一考さま
忘れていました。わたしの店の入っているビルはもともとは泥鰌屋だったのでした。昭和初期の四階建てです。四階の端にはいまも粗末な畳敷きの部屋が残っていて、板を打ち付けた壁に裸電球がひとつ。四畳半のわりには大きな下足の棚があります。従業員がかわるがわる階段をのぼってそこで休んだのではないかと勝手に想像しています。ご存知でしょうが八重洲富士屋ホテルの裏はむかしは青果市場で、近くには「大根河岸跡」なんて碑も立っています。泥鰌屋があっても不思議ではありません。当時としては立派なビルだと思いますから、よほどはやっていたのでしょう。いまはお化けが出そうですが。
友人の「江戸っ子」たちに限っていえば、彼らに選民意識があるとはとても思えません。そのうちのひとりに泥鰌について尋ねてみたところ、浅草では昭和三十年代中ごろまでは「泥鰌売り」がやってきて家で味噌汁にして食べていたとか。見なくなったのは、第一にはたぶん近隣の田園で泥鰌が売るほどには採れなくなったからでしょう。これには農薬の影響があるかもしれません。それとやっぱりあの姿。洗濯機や冷蔵庫など生活が電化され日常に「清潔さ」が増すにつれ、ああいうヌルヌルしてなまなましいものはだんだん駆逐されていったと見るのが妥当かと思います。なにしろ都会生活はどんどんデオドラントになって、いまや魚は生き物ではないみたい。
一考さんのご質問の趣旨とははなれてしまいました。
泥鰌とちりめんじゃことが結びついていたとは想像もしていませんでした。反復反復のちりめんじゃこにまぎれた異物がモンダイなのなら、泥鰌の場合は泥鰌自身が都会の異物なのでしょうか。
味噌汁の浅蜊に1個まじったシオフキだとか、浅蜊の身に隠れていたちいさな蟹だとかを見つけたときは妙に嬉しかったものです。ただこの嬉しさの感覚は一考さんの仰る「ひとり横むいたオットセイ」とはすこし違うような気がいたします。
泥鰌と蕎麦とはきっとどこかで似ています。
ちりめんじゃこにはその一匹いっぴきに目がついているのが印象的です。
一考さんにとってのちりめんじゃことは、安部公房の「砂」みたいなものなのですか?
ひとつひとつの目が、「世間」みたいなものなのですか?
« 前の記事「しばしば書き込みをして申し訳ありません」 | | 次の記事「新潟麦酒」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

