 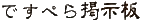 1.0 1.0
|
 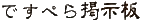 1.0 1.0
|
« 前の記事「酒井潔のことなど」 | | 次の記事「レンブラント、フェルメール、ゴッホ」 »
29日、佐々木幹郎さんの詩の朗読会に参加しましたが、アイルランドの詩人に託けて、氏が面白いことを語っていらっしゃいました。曰く、むかし神話と妖精は箇々の家庭にあり、人々と起居を共にしていた。やがて神話は国家のものとなり、妖精は死に絶えた。その神話を国家から取り戻し、妖精を蘇らせるのが詩人に与えられた使命である、と。
詩人のというより佐々木さんの格好良さに私は弱いのですが、それにしても大変な発言です。昨今の文学に喪われたものは個であり、その個を育みさらには突き放すセンチメンタリスムやリリシズムが肝要というのが私の持論なのですが、それとどこか通底するように思われます。センチメンタリズムやリリシズムが個の味方であれば、漱石の「自己本位」などというしみったれた文学しか生まれて来ないのです。時として寇なす輩であるがゆえに双方向の付き合いが可能になります。正義すなわち超人力と悪意の狭間に詩が棲息すると私は信じたいのです。信じたいというのは、どうもそういった弁証がなされない詩が増えてきたように思うのです。
「たまや」に掲げられた氏の「メアリーとダニーの庭」は、
この村で、午前九時に待ち合わせるなんて
そんな約束を守る奴なんて
誰もいない
の三行で閉じられています。イノセントと申しますか、アイルランド的な無邪気さと好い加減さ、そして「誰もいない」孤絶。どうやら佐々木さんの詩には「白痴的なまでの美しさ」が揺蕩っているようです。氏が郵便配達人の格好をして神話を各家庭に届ける、否小荷物はすでに届けられているのです。悲しいかな、妖精の死体とともに。
« 前の記事「酒井潔のことなど」 | | 次の記事「レンブラント、フェルメール、ゴッホ」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

