 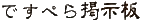 1.0 1.0
|
 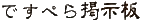 1.0 1.0
|
« 前の記事「ケンタウロス・サマーパーティ」 | | 次の記事「世迷いごと」 »
辻健さんへ
このところ悲しい話が続きますね。神戸も大阪も京都の街も、なべて未練や思い入れはないのですが、幼少期を過ごしたのは事実です。二十歳を経てからの上方には憎悪しかなく、栖を流転しましたのも、その憎悪すなわち自らの悔恨から逃れたい一心だったのかも知れません。若くして故郷を喪った者に安住の地などあろう筈もなく、またかかる地で心を許せる友を求めるなど烏滸の沙汰でした。いや、こんなことを書けば貴方や山本六三さんには礼を逸することになります。確かによき友を得ました。でも、友を得たら得たで、それは新たな拒否を、更なる拒絶の芽を自らのなかに生み出すだけなのです。落ち行く先で未知な友を拵えたところで、同じ消息の繰り返しとなります。
いかように託けようとも、ひとに存在理由はありません。ならば、友も同様にして、「私は友であった」と口にした瞬間に、友は指の間から砂粒のように零れ落ちてゆきます。「友であった」かどうか、逝った他者の真意を推し量るなど、欺瞞以外のなにものでもなく、もし仮に友たりえたとしても、相方の死と共にすべてのかかわりは消滅します。それゆえに、友の存在を退けるのが本音なら、友の死を悲しむのは建前ということになりましょうか。自らに対する偽善を厭うなら、暫時友は切り捨ててゆくのが自らへの、ひいてはその友への唯一のはなむけであり餞別になりましょう。ひとの死の悲しみと生きることの哀しみ、この両端を結ぶ橋は存在しません。かつての友というよりは戦友の死を前にして、悲嘆に暮れるなど我がままな振る舞いは許されるべきではないのです。彼が歩んだ思索者としての言動をいかに解釈し、いかに読み換えるか。山本六三さんに対して私に出来る供養と申せば、それを除いて他にはありますまい。
ちょっと切り口を換えてみます。「いかように託けようとも、ひとに存在理由はありません」と著しました。確かにひととしての個体には生きる価値も生き延びる理由もなにもないのです。すべては約束された滅びへのみちのり、「年々歳々花相似、歳々年々人不同」とはあまりにも犬儒的になりましょうか。しかし、確かにひとは変わり、最後は土塊へと昇華されてゆくのです。
でも、それら余りにも茫漠とした風景にひとのこころは堪えかねます。そこで編み出されたのが、世のしがらみです。しがらみとは柵(さく)であり、渡しであり、堰なのです。要は流動する心を塞き止めるためのノーハウということになります。謀と言って拙(まず)ければ方策で結構です。その方策の中に人は胡座をかき、かかわりの中に存在理由を見つけ出そうとするのです。今様のひとたちが携帯電話やパソコンを手放さず、架け渡された平面の交錯に刹那の自己満足を得たいと願うように、さらにはひとから必要とされる存在であるとの誤謬を自らに刷り込むために。そうした存在理由に、より確とした信憑性を持たせるために、しがらみは時と共に複雑化され、より錯綜したものになってゆきます。しがらみの最たるものが家族であり、仕事であり、友であり、金品なのでしょう。
さて、しがらみの対極に個があります。個が個であることの証明はひとつ、それは才能と権威の拒否です。才能とは実績に他なりません。さればこそ、実績を積めば権威が生じます。いわゆるその道のプロというやつです。プロに成り果せるのは容易ですが、それを拒むのは然るべき意志力が必要です。なぜなら、飯の種を自ら抛り出すことになるからです。山本六三さんは人生の後半、全力を傾注してやまなかった一群のタブローを一枚として売却しませんでした。否、値付けが高すぎて売れなかったのかもしれません。氏の本意がいずれにあろうとも、六三さんが個に拘泥しつづけたのは事実です。
志をもたない六三さんに同志やともがらは必要なく、人を愛する能力が欠落した氏に連れ添いや伴侶は本来不似合いだったのです。また、特定の趣味を持たない氏に常に親しく交わる仲間の要もなく、定めのない氏の生き方に従者や道づれなど生じよう危惧すらない筈だったのです。もっとも、それらの要因を構成する六三さんの性癖や奇矯な癖については著すひとも多くあろうかと思います。ことさら屋上屋を架す必要はなく、また氏と私とのかかわりはそのようなものではなかったと信じております。
私が山本六三さんとお付き合い願ったのは十六歳から澁澤龍彦さんに「銅版画のマニエリスト」を著していただくまでの十余年間、すなわち六十三年二月から七十七年六月までなのです。その澁澤さんのエッセイがお気に召さなかったらしく、掲載された「芸術生活」の上梓を契機に、また生田耕作とのトラブルを遠因に、私は彼との間に距離を置くようになったのです。澁澤さんにお書きいただいたエッセイは今なお正鵠を得たものであり、彼への好意に満ち溢れた文章と解釈しております。それなのに、「お節介」との小言を頂戴致しました。絵描きとはかくまで文意が読み取れないものかと、当時いささか辛い思いをさせられました。言われたことの内容ではなく、その時の六三さんの反応が私を裏切るものだったからです。五十人のひとがいれば五十通りの、百人のひとがいれば百通りの自分が生まれます。自己にとって他者とは常に多面性を内包した鏡、それを裏返せば自己とは他者の投影ということになりましょうか。思い込みとひとの評価の落差に身を曝してこそ、そこにエネルギーが、精神の運動が生まれると、これは花田清輝や石川淳からわれら共に学んだところのものでした。マラルメのエロディヤードを好んで朗誦していた六三さんはメタフィジックの信奉者なのです。だからこそ、そのメタフィジックを意識的に操作しようとしたのではなかったのか。少なくとも、私はそう理解していました。
しかるに、澁澤をして「もしかしたら、この画家は技巧に執するあまり、画面の背後からにじみ出てくるすべての曖昧なものを、潔癖に拒否しているのではないか、と思われるほどである。目に見える線や形に執するあまり、目に見えないメタフィジック(形体の背後にあるもの)の襲来を、意識的に阻止しているのではないか、と思われるほどである」と看破せしめた山本六三が韜晦を失い、一瞬たじろいたのです。躊躇いをひとに晒し、誤解を懼れた山本六三さんを目にしたのは後にも先にもあのとき一度だけなのです。澁澤をもしくは自分自身を嘲笑する、否、嗤いとばす方が彼には相応しかったのですが。
実はその後の消息はつまびらかではないのです。東京から西明石へ転じ居酒屋を営みはじめる直前、山本芳樹さんから連絡をいただきました。芳樹さんによると、六三さんの体調思わしくなく、いまのうちに是非会っていただきたいとのことでした。拙宅での再会はおそらく十七、八年ぶりだったと思われます。その晤語の内容はいまなお著すつもりはないのです。ただ、生田耕作のこと、過去の友人に対する痛烈な批判とともに、六三さんが私に対して抱きつづけた信義とそこから派生した苦衷を聴かされ、小一時間私は涙がとまりませんでした。それからは西神のお宅へもなんどか伺い、タブローを観せていただきました。お世話になったこしかたへの埋め草のひとつとして東京での個展を画策、まずは「銀花」や「太陽」「幻想文学」などで紹介をと念じ、幾人かの編輯者を紹介致しました。しかし、六三さんの好悪は予想以上に激しく、頑なな姿勢に個展の話は途中で断念、その詳細もここでは触れたくありません。ただ、相手が山本六三なればもっと違った遣り方があったろうと、済んだことを申しても詮無いのですが、私の組み立て方が稚拙だったと反省しきりで御座います。
徒し事はさておき、本題に入りましょう。まず、彼がなぜ具象の世界へ入っていったのか、なぜ巧緻な技術を前面に押し出すしかない作風に自らを追い込んでいったのか。往々にして華麗としか言いようのない、あまりにも耽美的な作品を前にして澁澤同様私も考え込まざるを得ないのです。若年にして非凡な懐疑精神を持っていた山本六三さんが、なぜ自らの技巧と卓越した美しさを無批判に信じるに至ったのか。思想と作品との間に横たわる大きな乖離をいかに解釈し、咀嚼し、また自らに言い聞かせて来たのか。澁澤さんのエッセイの「白痴美の銅版画家」の一言に彼は立腹しました、山本六三の思想を読み解いていない、無視していると。さればこそ、そこのところの乖離、自己撞着をつつきたくなるのです。
私は六三さんと面識があるからよろしいのですが、六三さんの画しか知らないひとには六三さんのメタフィジカルな面を窺い知ることはできません。作者と作品とのあいだの架け橋、すなわち弁証を彼自らが断ち切っているからです。かかる種類の画を描くという選択、その選択をもって自らの立場の闡明としたのが山本六三なのです。それはディレッタントの常套手段であり、怒りを私に宣した瞬間から、彼は好事家の、趣味人の道を一人歩むことを宿命づけられたのです。言い換えれば、思索者としての側面への評価を抛り出し、孤高の画家としての立場を自ら選び取ったということになるのです。そこのところの消息が彼にどこまで理解できていたのか、はなはだ心許なく思うのです。ひとを傷つけまいとする澁澤さんの目くばり気くばりの行きとどいた文章に対して六三さんがもし胸襟を開けば、私とのかかわりも異なったものになっていました。その点に関して六三さんとのあいだに対話が持てなかったことを残念に思っているのです。もっとも、人品骨柄の批判に類する議論を闘わせるのは六三さんとは不可能でしたが。
貴方もご存じの三橋敏雄さんに「顔押し当つる枕の中も銀河かな」という句がありますが、ここには文学の要諦のあらかたが示唆されています。「枕の中が」であれば興は褪めます。「枕の中も」と閉じることによって、大宇宙の銀河と枕の中の銀河とが融合するのです。ここでは大きな銀河と小さな銀河とが、入れ子構造となって立ち顕われます。すなわち、大と小の弁証法が十七文字に昇華されているのです。「枕の中」から滲みでてくる曖昧なもの、押し寄せるメタファーの洪水、それこそが、六三さんの画に私が求めてやまなかった唯一の主題だったのです。私が知り合ったころの六三さんは辻潤を愛読し、荘周の夢物語を枕頭にシュルレアリスムに遊び、二項対立が対立でなくなるような一種の球体感覚を追求していました。二十代の頃の彼が立ち徘徊る情念の場にはめざましいものがありました。弁証につぐ弁証、繰り返される懐疑のなかでふつふつと沸き上がる自己欺瞞、ともすれば消え入ろうとする自己を支えるための韜晦。斟酌せず、生死を呵責し、自らを追い込んでゆく姿勢に私は讃歎し、驚愕させられたのです。
にもかかわらず、氏にとって自意識における弁証の対立項に大きく立ちはだかったのは与り知らないところの影のような他者だったようです。反語めきますが、六三さんにとって思うに任せぬ他者とはほかならぬ山本六三その人だったと申せばあまりに悲しい話になりましょうか。彼は山本六三という名の男を、他との関係においてのみ在るもの、一定の関係、一定の状況においてだけ妥当するものとして咀嚼せず、そこに絶対値としての存在を夢見るようになっていったのです。自らの相対化を潔しとしなかった彼は「ひとは変わらないよ、変わるものじゃないよ」との言葉を呪文のように口ずさむようになりました。
ある日を境に、氏にとって山本六三は常に変わらぬものとしてそこに存在しつづけたように思われます。そうした自己の固着には大きな落とし穴が待ちかまえています。撞着も懐疑も本来自己に向けられ、我とわが身を穿つための知的水準器であり掘削機なのです。旺盛な懐疑精神は自己解体と再構築の繰り返しを間断なく強要します。自己と他者そして自身の作品との三つ巴の弁証法を構築するか、もしくは二項対立を際限なく増やすことによって自らの立ち位置を意識的に見失うような方法論を薬籠中のものにすれば、もう少し自在に振る舞えたのではないかと思うのです。ディレッタンティズムやダンディスムといった鎧のような安っぽい固定観念から解放され、新たな精神の領域が立ち顕れたに違いなかったと思うのです。
繰り返しますが、西脇順三郎や吉岡実、稲垣足穂や石川淳、土方巽や寺山修司に見られる過度なまでの方法論、固着した精神や趣味性を呪い続けた彼等の瑞々しい屈折、固執を厭い休むことなく揺れ動く伸縮自在な発想、そうした自らへの懐疑のみが思想ではなかったのか。それこそが、かつて六三さんから剥ぎ取り刮げ落とし簒奪した私の思想であり、また、山本六三そのものであったにもかかわらず。どうやら早熟な六三さんはスポイルド・チャイルド世代固有の自己疎外に苛まれ、「人は終生変わらない」という精神の荒野に足を踏み入れてしまったようです。
「勉めて何者かであろうとするタイプと相対するところの者に合わせて何者にでもなれるタイプと二種の人品があるように見受けられます」これは私の口癖です。六三さんと出逢い、私は六三さんと同化したいと願いました。自己解体が私のなかで繰り返されたのです。その解体によって私は「相対するところの者に合わせて何者にでもなれるタイプ」を撰び取り、六三さんは否応もなく、勉めて山本六三であることを強いられたのです。もちろん、それを強いたのは私ということになります。友という眷恋の情が、ひとを慕い募るこころがひとをあやめる。塚本邦雄さんの「感幻楽」に「馬を洗はば馬のたましひ冴ゆるまで人恋はば人あやむるこころ」との句がありますが、真に親しく接するとは互いの身を絶巓に押しやり、ときとして奈落の底へと背を衝くことになりかねないのです。友とはそして愛とは残酷なものです。はじめに「自らに対する偽善を厭うなら、暫時友は切り捨ててゆくのが自らへの、ひいてはその友への唯一のはなむけであり餞別」と著したのにはこのような事情が秘められていたのです。互いが互いを敬い、思慕するがゆえに、精神的には引き裂かれて行く。その距離に絶望を、あまりもの怖ろしさを感じたとき、私は六三さんの元を去るしかなかったのです。もちろん、彼の精神の躍動を跳梁を願っての行為であり、私にとっては一種の自傷行為のようなものだったのです。だって結果として、恋人を、もう一人の自分を失うのですから。
うつしよに旅人のかすかな息づかいを遺したい、かりそめの華を咲かせたいとの表現への思慕、表現への自意識、その強弱が表現者の呼吸であり、搏動であり、思想そのものなのです。若かりしころの彼の思索の痕跡、彼の精神の振幅、彼固有の特異な弁証法、そこのところを何時の日か私なりに綴らねばなりますまい。つらい仕事になりますが、おそらく山本六三という存在をなぞらえることが可能な一人に違いないのですから。
先頃、高柳重信さんの若書きに「戸田橋へ乾反葉走る切通」との句があるのを知りました。故郷の風景ををかくまで冷淡かつ冷酷に描いた句があったでしょうか。一切の帰属を拒否しつづけた高柳さんの壮絶なまでの覚悟、苛烈なまでの現体験が過不足なく著されています。この句に登場するのは風を身にまとった虚無のみ。いや虚無を携えた風でしょうか。切通しの彼方にも此方にも趣はおろか、情念のひとかけらすら存在しません。重信さんの句を引用したのは他でもない、高柳重信の名を十六歳の私に教えた人の名は山本六三。彼もまたマントの中に虚無をひそめて、さりげなく現れ、にこやかな微笑みを残して去って行ったのです。
追記。
本稿は「友の死に思う」と題して二00一年十一月十一日(日)にですぺら掲示板に掲載したものに加筆修正を施したものです。文章の一部は「残日を指折りかぞえて」と重複します。後者の文中で「主要な部分はすべて一人の男のために著されている」とありますが、その横須賀さんのご指摘どおり、山本六三さんを執拗に意識して書かれた文章が夥しい量にのぼります。理由はすべて文中にて触れています。従って、掲示板に掲載したものを糊と鋏でつなげれば一篇の山本六三論ができあがる筈だったのです。それは掲示板に対する私のささやかな企みでした。しかし、そこに問題が生じました、山本六三さんの死の直後にやってきた横須賀功光さんの出現と突然の死です。十六歳で得た友とそれから四十年を経て得た友と、そのデスタンスを埋めるのは不可能事と悟ったからです。横須賀さんはわたしにとって修復不能な裂け目のような存在であり、四十年の間に私の内部で繰り返された変化も大きかったのです。
同一の文章を用い、双方を並行して書き進める。そこから私の四十年間の自意識における乖離と撞着を追体験できるのではないかと思いました。一月十八日以降、十日間をそれに費やしました。書き終えたわけではありませんが、取り敢えずの段落をみました。 今一人の友、辻健さんにお読みいただければと念じます。なお、現在存命の人に触れた部分はすべて削りました。
« 前の記事「ケンタウロス・サマーパーティ」 | | 次の記事「世迷いごと」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

