 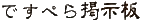 1.0 1.0
|
 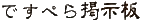 1.0 1.0
|
« 前の記事「高柳重信展のことなど」 | | 次の記事「また来ました。」 »
震災の後のおしゃべり
読み手をどこかへ連れていくような、物語の楽しさはもちろんですが、
装丁の美しさ、限定出版された書物の希少性、そして、さまざまな立場で本と接する人々……もっと多面的な本の魅力について、お話しましょう。
美しい書物
未曾有の大震災に襲われたのは一月十七日、明石の拙宅も甚大な被害を受けました。屋根が崩れ落ちて瓦は一枚も残らず、風呂場と便所は壁の裂け目から星の瞬きが見えるようになりました。電気、ガス、水道、電話、ライフラインのすべては途切れ、露天風呂と化した風呂桶に残された僅かな水が全財産となりました。数十年かけて蒐めた焼き物や薩摩切り子のコレクションも全滅、大事にしてきた書物も書棚もろとも顛倒して、未だに手つかず。足の踏み場もない書庫から取り出せた数部の書冊も、函が壊れたり、表紙が破れたり、ねじ曲がったり、ことのほか不憫に思われます。
電話が通じるようになってからのことですが、「大丈夫なのか」との問い合わせを随分と頂きました。やがて、馴染みの古書店や出版社の知己から義援金が送られて来、京都在住の友人は飲料水と屋根に掛けるシートを山のように抱えて、福知山経由で丸一日を費やして見舞いに来てくれました。友曰く「おまえが死のうが生きようがどうでもよろしい、ただし、この家には国会図書館にない本が多数ある。まず本を救わねば」彼はさっさと屋根に攀じ登るとシートを拡げ、傾いた襤褸屋をあっという間に「青色の館」へと変身させました。彼だけではありません。前述の「大丈夫なのか」も、大半は「先に本を救え」「屋根だけは何とかしろ」の類で、私の怪我のことなどは誰一人問いただしもしません。どうやら主語は本であるらしく、この家の主人は家中に巣くう夥しい書物なのであって、決して私ではなかったのだと言うことに気づかされました。
本と付き合いはじめてから今日に至るまで、読書に始まって、編集、出版、装丁など、さまざまな形で書籍と接してきました。若い頃に泉鏡花を知ったのが、本好きになるきっかけになったと思います。鏡花本は美しい、実に美しいものです。鏡花本の悉くは鏑木清方や小村雪岱の版画で飾られています。あの時代は絵師に彫り師、摺り師が多く居ました。和紙も廉価で、条件が整っていました。著者自身も装丁には腐心しています。本の内容がメッセージだとすれば、装丁はメディアです。夏目漱石や鈴木三重吉、与謝野晶子はそれを自覚した作家でした。北原白秋、木下杢太郎、竹久夢二、渡辺一夫、北園克衛、吉岡実などは自らの著書にとどまらず、数多くの装丁本を遺しています。内容に相応しい装いに焦がれたのだと思います。著された原稿や作者の想いに一つの形を与えるのが装丁です。配された文字の大きさとバランス、色や紋様、あるいは素材の風合いや感触が中身と照応しあうとき、美しい書物が誕生するのだと思います
罰せられざる悪徳
すべてのきっかけはサルトルでした。
私が中学一年か二年の頃のことです。風邪をひき、かなり高熱を出して寝込んでいる所へ、母が本を買って来てくれました。近所の本屋で薦められたからと渡してくれたのが、人文書院から上梓されたサルトル全集。その一冊に「嘔吐」があり、巻頭にセリーヌの言葉が掲げられていました。セリーヌって誰だろうと疑問に思い、手に入れた「夜の果てへの旅」今は懐かしい大槻鉄男さんの翻訳でした。そのあとがきに出てくるサドの名前。ついで買ったのが澁澤龍彦訳の「恋の駈引き」あとがきには、サドの系譜に属する作家としてポウ、カフカ、石川淳が著されていました。そうやって、本に名前が挙げられた作家の作品を、片端から蒐めていくうちに、私は本の世界にのめり込んでしまったのです。
ヴァレリー・ラルボーに「罰せられざる悪徳・読書」と題するエッセイがありますが、そのタイトルは読書の醍醐味を的確に表した言葉だと思います。男色も、盗みも、殺人も、読書に比べれば、随分と柔な悪徳です。サドの「ソドム百二十日」では三十人がむごたらしい拷問に遭って絶命しますし、登場人物がすべて殺されてしまう著名な探偵小説はみなさんもご存じでしょう。如何にいかがわしい夢を見ようが、また、おぞましいことに身を委ねようが、書物の世界ではすべてが許されるのです。
唐十郎さんが面白い話をしてくれました。彼が子供の頃のことですが、湘南海岸に泳ぎにいきたかったのだけれど、家が貧しかったので湘南までの電車賃がなかった。そこで、洗面器に張った水に湘南への想いを託した。それが文学への第一歩なんですね。電車に乗って湘南へ行くことと洗面器に顔を浸けることとが等価になる。即ち、想像の世界と現実の世界とが等しくなる。そういう人こそ、書物を繙く資格があるんです。夢と現実が相克すると思っている人は、本を読むなんてのっけから止めたほうがいいと思います。
これが文章を著すという段階になると、洗面器の中に、湘南海岸どころか、全宇宙を視てしまう。そして、湘南海岸はああだこうだと活写する、実に稠密かつ緻密にですよ。つまり、見てきたような嘘を書くわけです。生活なんてどこかへ捨ててしまって、書くという行為そのものが唯一の経験になり生活になる。空想と現実との境界線をなくした寄る辺なき身、いわば汽水域に生きる白魚のようなもの、もしくは昆虫でもあり植物でもある冬虫夏草のような存在を想像すればいいわけです。
三橋敏雄さんに「顔押し当つる枕の中も銀河かな」という句がありますが、ここには文学の要諦が示唆されています。「枕の中が」であれば興は褪めます。「枕の中も」と閉じることによって、大宇宙の銀河と枕の中の銀河とが融合するのです。ここでは大きな銀河と小さな銀河とが、入れ子構造となって立ち顕われます。即ち、大と小の弁証法が十七文字に昇華されているのです。
そして、大好きな泉鏡花ですが、鏡花の小説は読んでいて血沸き肉踊ります。読み手をどこか別の世界へ連れていってくれます。「高野聖」で、鬱蒼たる森の中、空から雨のように蛭が降る場面なんか、ありそうにない話だと分かってはいても、思わず背中をまさぐりたくなる。描写力が読み手をぐんぐん引っ張っていく。見たこともない、行ったこともない、そんなすごい所へ連れていってもらえるのが嬉しくて、私は本を読むのですから。
そして神戸
文学に夢中になった坊主頭の中学生は、つっかけを履いて足しげく古書店へ通うようになりました。当時は詩に興味があったものですから、詩書をずいぶん購入しましたが、他方、仏蘭西文学や花柳界を舞台にしたいわゆる「遊蕩文学」をごっそりと買い込みました。歳格好に似つかわしくない本を買っていたからでしょうか、古書店のおやじから声を掛けられたり、懇意にしている作家を紹介してくれたこともあります。澁澤龍彦さんもそうして知り合った一人です。
京阪神の古書店では飽きたらず、お金を貯めては東京へもよく出掛けました。落合の某古書店へモダニズム関係の本を買いに行ったときのこと。書架に並べられた本を見ながら、目的の書冊を次々と引っ張り出して、その数五十冊にもなったでしょうか。店主がやって来て、「ぼく、これ買うの?」当時はまだ十代でしたから、怪訝に思ったのでしょう。「はあ、買いますよ」と答えると、「あんた、誰」「あの、渡辺っていいますが」「渡辺って……、まさか、あの神戸の渡辺さん」その店も通信販売で頻繁に利用していたので、名前は覚えていたのでしょう。「渡辺さんって、五十過ぎの方だと思っていました」
私が驚いたのは、その日、お茶を馳走になりながらの希本の数々である。「先行き、あんたはこういう本を買うようになるんだから、よく見ておきなさい」と言いながら、永井荷風が愛人に贈った署名本や白秋宛て朔太郎の署名本、伊良子清白の詩集「孔雀船」署名本等々を観せて頂いた。
書物は恋人
二十歳の頃です。どうしても欲しい本が明治古典会に出品されるとの話で、蔵書の半数を占めていた詩書を纏めて売り払いました。書肆ユリイカの出版物を中心に、戦後詩の主なものは大体揃っていました。年収の五倍位の大金を得て、念願の平井功の二冊の詩集、「サバト」「戯苑」をはじめとする日夏耿之介の編輯になる諸雑誌一括と日夏耿之介の詩集一口を購入しました。
時には蔵書を売って、あるいは古書店に借金をしてでも、読みたい本は手に入れる。そんな私の本好きは、読むことからやがて造ることへと拡がっていきました。そもそもが、一部分だけ担当するというのが好きじゃないので、本を造るのも、構想を練るところから書店への販売まで工程すべてを手掛けなければ気が済まないのです。なにがしにはあの翻訳を、この人には懸かる種類の創作を、まずはそんな所から始まります。そして、原稿をとってきてレイアウトを施し、朱筆を持って校正し、自ら装丁します。最後は風呂敷にくるんで営業に歩き回るのです。
ところで、二千部の新刊を造ったとします。売り先は、東京都内で千五百部、京阪神で百部、その他の地域は全国津々浦々すべてひっくるめて百部。残る三百部は五年ほどかけて、東京で徐々に捌けていきます。つまり、出版は東京以外の地では成り立たないのです。南柯書局の仕事もなかなか厳しく、ついには印刷会社への支払が滞ってしまいました。一億を軽く越える金数を費やして、残されたのは支払う手立てのない五百万円の赤字と在庫の山。東京の出版社から「借金を肩代わりしてやるから、おまえ、うちの編集長になれ」と声を掛けられたのは、丁度そんな時でした。そこで私は東京へ身売り、三十代も後半のことでした。
考えてみると、本に夢中になってから今日に至るまで、東京へ夜逃げした頃だけが、唯一借金から解放された時代です。他はずっと、古書店の借金を抱えていました。欲しい本のためには借金も厭わないのですから、仕方がないのですが、借金をあまり気にせずにいられるのは、古書店側が平気で借金させるのも原因のひとつです。というのは、もし借金が払えなくても、古書店は本を差し押さえればいいからです。気が置けない古書店の中には、年末になると車でやってきて、借金分だけ本を持っていってしまうところもあります。稲垣足穂の署名本もそれで失いました。借金のかたに本を持っていかれるのは辛いものです。きっと、私が死んだあとは、一冊残さず持ち去るに違いありません。それも二束三文で。でも、真っ先に義援金を工面してくれたのは、その古書店なのです。本の売買と同様に、古書店との付き合いは行きと帰りの両面に亙ります。どちらかが往生するまでの、義理も人情もある愉快な道中です。
大風呂敷
人って、表に出す人もいるし出さない人もいるけれど、大概自分のことを自慢したいんです。自己表現と自慢は一枚のコインの裏表。例えば、私が書物にのめり込んだのも、それは、こんな美しい本があるとか、こんな素敵な本ができたとか、つまりは「すごいだろう」って自慢したいだけなんです。
何かしている、何かに夢中になっている時って、充実しているじゃないですか。どう顛んでも人の一生なんて、「質の悪い冗談」でしょう。行き先には滅亡しかないんですから。生き甲斐なんてあるわけないですよ。だからこそ、死に至る過程を如何に楽しむかが問題になるんです。それはスタイルであり、なりふりの問題です。例えば、人と話をする時に、信じるべき自分、話すべき自分なんて、どこにもないわけでしょう。でも、それでは会話が成り立たないから、その間だけ無理矢理自分を構築するんです、自分はこうなんだと。要するに、相手の思惟の対極にわが身を置くんです。総論反対、各論絶対反対ですね。そうすると、話をしている間だけは「自分」がある。本来、存在していないに均しいものが存在感を感じる。これ以上の錯覚、これ以上の快感はないと思うのですが。
本でも、金魚でも、自転車でも、料理でも、何でもいいんです。なにかしている時って、それに没頭出来るじゃない。そして、自らしていることに意地を張れる。人生なんて、あるがままでは意地の張りようがないけれど、そこに何か項目をつけ加えれば、意地も見栄も張れるでしょう。謂わば限定版の人生をでっち上げるようなものです。むきになるとか、風呂敷を拡げるって、楽しいじゃないですか。そんな時だけですよ、人生がキラキラ輝いてみえるのは。
渡辺一考(わたなべいっこう)昭和二十二年二月五日、兵庫県神戸市生まれ。
« 前の記事「高柳重信展のことなど」 | | 次の記事「また来ました。」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

