 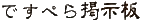 1.0 1.0
|
 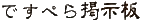 1.0 1.0
|
« 前の記事「金子國義個展」 | | 次の記事「25日の「新日曜美術館」」 »
一昨日、久しぶりに鱒助(マスノスケ)を櫻井さんと食べた。「かさね」からの差し入れである。マスノスケは六月から七月にかけて北海道沿岸で主として定置網で漁獲されるキングサーモンである。岩手や宮城ではダイスケもしくはオオスケとも呼ぶが、非常に数が少なくほとんど一般の市場には出回らない。
キングサーモンはアムール、カムチャッカ、アラスカ、カナダからカリフォルニアまで分布するが、ロシアに回帰する一部が北海道で漁獲される。鮭の仲間では最大種で、全長一メートルを超すものも少なくない。かつて北海道でも放流が試みられたが、成功しなかった。
昨今、スーパー等で比較的安く販売されているキングサーモンは外国産の海中養殖魚で、マスノスケとは食味が異なる。マスノスケには鮭特有のまったりした食感があまりなく、さわやかな舌触り、淡泊な味わいはウトロ産の鮭児とは正反対に位置する。全身これ大トロの鮭児は年間四、五百匹しか捕れず、羅臼市場のセリ値で一尾数万円になるという。しかし、マスノスケは値はともかく、さらなる貴種である。鮭児を本マグロの大トロに見立てるなら、マスノスケは銚子沖でとれる近海ものの鮪の淡い赤身であろうか。春先から秋にかけての産卵前がことさら美味、ソフィストケーテッドな味わいにいつも愕かされる。
鮭ついでに、「スケ」とは、「サケ」の語源であり、地方によっては鮭の中でもとくに大きなものを指す。また、「スケ」は「介=大将」の意であり、サケ・マス類中最大となる本種が「鱒の介(大将)」であるといわれる。
知床の「鮭児」、日高の「銀聖」や「時鮭(ときしらず)」、羅臼の「いばらの内子」、鵡川の「シシャモ」等々、北海道ではいろいろな珍味を教わった。そう云えば、横須賀さんはですぺらに残っていた「いばらの内子」を来るたびに食されていた。内子の在庫が無くなったとき、それが彼の命日であったように思う。
« 前の記事「金子國義個展」 | | 次の記事「25日の「新日曜美術館」」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

