 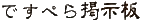 1.0 1.0
|
 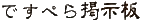 1.0 1.0
|
« 前の記事「ウイルス情報」 | | 次の記事「ウイルス」 »
奥歯さんへ
敷衍曲と題するつちのこ編集者の戯れ言第三弾。例によって、奥歯さんへ託けての戯れです。
かつて郡司正勝さんは日経新聞の「オリジナリティーとはなにか」とのアンケートに応えて一言「オリジナルなんてありません」。また貴女がお好きな澁澤さんはオリジナリティーを過価なるものとして嗤い飛ばしていました。確かに貴女が仰有るように、文学と哲学にはパラフレーズとの言葉が似合います。ただし、敷衍ではなく、敷衍曲の方がより相応しいでしょう。
金子千佳という詩人を私は存じ上げませんが、結構な詩です。男女の稟質の違いがよく表現されていると思います。素敵なイントロです。
第一節からはじめましょう。まず『「人が考えたから考えなくて済む」をいうわけにはいかない領域こそが哲学であり文学』であるとの御指摘。「いうわけにはいかない」を「それを言っちゃあ、お仕舞いよ」と転じ、「言えねえところが文学よ」と結ぶ方が通りがよくなります。冗談はさておき、物理学にせよ天文学にせよ、大方の学問は類推の上に成り立ちます。例えば天体の運行をつぶさに観察し、任意の一点にブラックホールがなければ、運行の整合性が得られないと言った案配です。現象を統一的に説明することが可能な仮説をまず打ち立て、それを検証し、妥当するところの真理を導き出すのです。
一方、人間には先天的な概念と後天的な概念とが混在します。でも、人生に仮説としての設計図はないのです。人はまず存在ありきで、生きて行く課程で双方の概念が絡み合って概念構成がなされて行きます。サルトルが示唆したことは半分正しく、半分は間違っています。その問題点の整理は後日述べるとしましょう。
文学は書き手個人の倫理観、価値観、歴史観を綴るものであって、アナロジーもしくは一般化とは所詮馴染まない領域のものです。三島由紀夫の死と共に三島の文学も終了するのであって、三島文学とは三島由紀夫の存在そのものだと申せましょう。要するに、百人の物書きが居れば、百通りの文学が存在するのです。だとすれば、他者が著した文学なり哲学を以て自らを諾うには常に危険が伴います。特定の他者にいくら恋い焦がれたにしても、すべてのシチュエーションが重なり合うような人生はおそらく望むべくもないからです。仮に体験に頗る似通ったところがあるにせよ、それを読み換える変換機能としての内的体験までが同じというのはおおよそあり得ないことです。従って、文学にあっては他の学問に見られるように類推が入り込む余地はほとんどないのです。
「人が考えたから考えなくて済む」のが思惟の結果なら、その推論は個人の否定になりますし、そうでなければ、内包した自家矛盾にも気付かない不自然な存在、即ち馬鹿者ということになります。いずれにせよ、支配されるのを望むファシズムの立派な構成要員なのです。もちろん、考えたからと言って何が解決されるわけでもないのですが、それに関する発言は後段に譲ります。今一つ、類推とイマジネーションの問題がこれでは解決されませんが、属性に関する類似の否定が、イマジネーションを羽ばたかせるのではないかとだけ指摘しておきます。
第二節と第三節は言葉とその概念の問題です。これはどこかで触れたので繰り返しませんが、「言葉はアリアドネの糸です。思考の軌跡を残しておかなければ同じところをそれと気づかぬまま何度もぐるぐるまわるだけにもなりかねません」の中の「思考の軌跡を残しておかなければ」はとても大事な文言だと思います。ただし、文意は貴女とは異なります。
「独語録」か「三位一体論」が貴女の脳裏を去来しているのでしょうが、同じところをぐるぐるまわるのは単にその人の頭が悪いだけであって、気付こうが気付くまいが大した問題にはならないでしょう。問題は思考の軌跡です。
言ってしまえば文学好き、されど思想のない文学なんぞ読みたくもない、そこまでは問題ないとして、考えるとの行為すなわち思考が迷いであり、逡巡であり、躊躇いであると、恐らくこの定義も問題なし。ただし、なにが迷いなのか、なにを持って逡巡とするのか、なにをして躊躇いと名付けるのか、ここには個体差が生じます。その逡巡の過程を取り敢えず試行と名付けましょう。試行を包み隠さず書き著すことによって、読者は筆者の搏動即ち個体差を識ることが可能になります。逆に言えば、包み隠さず綴られた試行は個体差を認識した人の生存の課程であり、まさにドゥルーズのいう流動の相の自ずからなる表明になります。また、搏動とは個としての書き手の生の証しに他ならず、搏動を伴わない文学とはその意の通り、思想のない文学ということになります。……と書いてきて、貴女との亀裂をいつも思い浮かべます。「なぜ、思考が迷いなの」との質問を度々受けます。一方、私はよく懐疑との言葉を用います。私が用いる「懐疑」はヘレニズム時代の懐疑派のそれとは全く異なります。私は個人的平安を与える処世術や思い煩いのない平常心など求めていませんし、判断中止に陥ったこともありません。より重要なのは思考にいかなる形であれ、結果や結論を求めていないという点です。懐疑が思考のエネルギーの唯一の源ではないかと思っているだけなのです。
自己に懐疑を差し挟まない、言い換えれば、自己を信じて疑うところがない、否これは言い過ぎかも知れません。でも、例え博捜の上、自己の立場を見出したにせよ、状況は同じでしょう。たどり着くとの概念自体が私には胡散臭くかついかがわしいものに思えるのですから。ピュロンが言うように、確かに言葉への不信は人間不信に直結します。そして、真理の探究、本性の認識は不可能だと私も思っています。西洋で哲学がその目標とエネルギーを新たにして甦る時、否定するにせよ、肯定するにせよ、必ずキリストの問題が立ち顕われます。私は日本で生まれ、日本語で育ちました。キリストという概念が希薄ですし、キリスト教の文化と伝統も審らかにしません。でも、好奇心は旺盛です。その好奇心が私にエポケーを拒否させるのです。懐疑の原語である「スケプシス」skepsisというギリシア語は元来探究という意味でした。真理の探究は無理でも、生きた人間すなわち戦友の苦衷には大いに興味を抱きます。この点に関しても後日述べます。
第四節に問題なし、第五節の「言葉を軌跡としてただ飛べばよい」は貴女らしい詩的な文言ですが、それこそ飛んじゃっています。おそらく「名前、自己同一性、そんな重いもの」からの脱却を示唆しているのだと推察します。昔、安部公房が「砂の女」でこの問題と格闘していたのを憶い出します。弛緩した文学者が陥る二律背反を「夢見のわるい道学者」と論断し、止揚としての実作者を「俳に濡れそぼるシュルレアリスト」と讃じたのは加藤郁乎さんですが、同じ飛ぶなら今少しなりふりを構いましょう。
第六節の『フラットな世界が「すべては同じ」』には重なり合う問題点があります。私が試みたのは、価値としての等価を認識することによって存在そのものが滲透し合う、言い換えれば、孤独や失意の中に溶解してゆく自分の様を言いたかったのであって、ひいては人の存在には価値がないとの立論を示唆しようとしたのです。ところが、貴女は「同じ」ではなく「すべて」に論点を移しています。私が用いた「すべて」は「人の存在には価値がない」との立言に例外はないということを強調したまでなのです。ここでの「例外はない」は自己に懸かってきます。自己の内部に向かわない思惟なんぞ、机上の空論に過ぎないのですから。幻想文学でも著したのですが「他のいかなる人間とも完全に等価である」ということを識った時、人はまず苦悩に陥ります。「そんなことを認めてしまえば、今までの私は一体なんだったのか」との疑問に逢着するからです。等価は今まで当たり前の存在として容認してきた自分をまず否定することになります。大仰な言い方をすれば、等価への認識は人間存在の極限、絶望の果てを意味します。しかし、かかる境地の向こう側には風通しのよい球形の荒野が拡がっているのですが。
繰り返しますが、「すべて」との言葉を用いたのは論理的整合性を強調するためではなく、また他者に向けての物言いでもないのです。自分に対して「例外はない」「等し並」であると言い聞かせる、自分自身へのイエロー・カードの随時発行であり確認なのです。同列、同様、一様との文字を私が好んで用いるのも他者と自己を差別したくない、もしくは差別など出来る筈がないとの立言に則ってのことなのです。「すべての存在は虚しい」それが「大雑把すぎ、楽すぎ、危険すぎ」るものの考え方なのでしょうか。
第七節は難解です。特に「無数の価値体系を同時に持つことによって、どこにも帰属しない無意味なオブジェとしてすくいあげる」この文意は私にはよく解りません。経験を抽象そして捨象することによって得る概念であれ、経験から独立した先天的概念であれ、「無意味」との概念上の文言と価値体系を強いられるであろう「帰属」との関わり合い。「価値」に含まれる「反価値」と「無意味」との関わり合い。そして「無意味」と「価値体系」との関わり合い。最後に「無意味」と「オブジェ」との関わり合い、その辺りが私には読み切れないのです。主旨が単数の立言とは限らない、これは若い人の文章に多くみられる欠点のひとつです。そういう場合は文章を長くし、論点を分割するように心掛けるべきではないでしょうか。結論を急ぐのはよくないことですし、結論を導き出さない方が説得力が増す場合すらあるのですから。
概念は確かに意味として存在するのですが、表現する際には言語になります。いかに「優れた」と予想させる思想であっても、表現が拙ければ、それは拙い思想にしかならないのです。なお、価値体系における優劣の階層的序列に私はなんら興味を抱きません。そんなものは端から信じていません。それは貴女がよくご存じの筈。
第八節の「振幅」はムーンさん宛の「ガラガラポン」に記載。
「思考は螺旋を描いて下降し、地獄巡りがはじまる」これにはちょっと異議あり。思うに、貴女の頭の中にはアウグスティヌスやダンテのイメージがあるのでしょうが、幸田露伴や稲垣足穂のシャボン玉やパンティを括りつけた風船を千里の空に飛ばした下着デザイナーの鴨居さんのようなパラフレーズの方が、夢があって楽しいではありませんか。「地獄巡り」は好みではありません。
もう一つ、「言われきったこと、書かれきったこと、それはもはや目的ではなくて手段です」にも異議あり。既に口に出したこと、書き著したことはさほど重要でなく、大事なのは今現在の思惟なのでは、ということが仰りたいのだと思います。でも、思惟は生き延びるための数少ない手立てではあっても、目的ではありませんし、思惟そのものにも目的はないと思うのですが。人の生、即ち人の存在に目的や価値がなにも無いのと同様です。たって申せば、滅びるためとでもしておきましょうか。
終章の二行に関してはゆきちさん宛の文章で触れました。自己と他者の問題は安直に境界線が引けるようなものでなく、片側だけでは議論の対象にすらなりません。それは自らの主辞と賓辞を繙くことにもなりますし、それだけでも数冊の書物を著すことが必要になります。前記文章ではあくまでかかわりのカラクリのひとつを述べたに過ぎませんが、誤解を畏れずに結論のみ申せば、「人は人の望むところのものになるしかない」ということになりましょうか。きっと、お付き合いした人の数に比例した複数の貴女が、そして一考さんがあちらこちらで蠢いているのでしょうね。
他者が自らの鏡であれば、自己とは他者の投影、されば、言葉とは思考の酩酊なのでしょうか。
「考えたからと言って何が解決されるわけでもない」との疑問を前述致しました。それについて一言。話をマラルメに持って行きたいのでアナロジーから始めます。アナロジーは自動記述やデペイズマン同様、文芸上の技法としては有効です。マラルメの「イジチュール」からボリス・ヴィアンの「日々の泡」に至るまで、それこそマラルメの言う「類推の魔」を書物の世界から抽出し列挙するのは容易いことです。
「後方見聞録」所収の「西脇順三郎の巻」の中で「マラルメのメはまなこなり」との西脇さんの駄洒落を郁乎さんが引用しています。思うに西脇さんは洒落の達人で、とりわけ酒席における駄洒落の切れ味には怖いものがありました。「マラルメのメはまなこなり」にしましても、マラルメの散文詩におけるアナロジーの地歩を過不足なく示唆するに際し、他ならぬアナロジーそのものを援用するという芸の細やかさ。東大、京大、九大のノータリン学者(とりわけ「種の論理」を唱えたヘボ学者)が一冊の著書で著したことを一言の駄洒落で切って捨てる、頭脳というのはこのように使われなければなりません。かような高級な会話、即ち晤語の中で読解力の妙味を味わわせてくれる人を私は達人と呼びたいのです。
「考えたからと言って何が解決されるわけでもない」この文言は言い換えれば「読んだからと言って何が解決されるわけでもない」と同一の意味内容を持ちます。読者の智力が書き手のそれに肉薄するものでないかぎり、読書は虚しいものです。単なる時間の浪費でしかないのです。私事にわたり恐縮ですが、かつて限定本に興味を持つ人で読書力、読解力を持ち合わせた人と一度も出会ったことがないのです。そしてある日、南柯書局の一部の本がコレクターの愛玩物ないしは投資の対象と化していたのに気付かされました。私が出版を止める日が訪れたのです。
このような話を始めるととめどがなくなります。最後に繰り言を一言。櫻井さんがご指摘のように、年齢に相応しい覇気といいますか、負けん気の強さが望まれます。年長者に立ち向かう時は常に玉砕を覚悟しなければならないのです。破綻を懼れていては精神にダイナミズムは生まれません。そうして繰り返される抗いの果てにのみ、新たな精神の領域が立ち顕れてくるのです。
« 前の記事「ウイルス情報」 | | 次の記事「ウイルス」 »
|
ですぺら トップへ |
掲示板1.0 トップへ |
掲示板2.0
トップへ |

